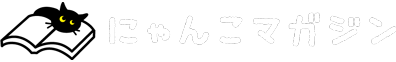第13回 猫救出作戦
「名前は?」
「チャー子です」
「何才ですか?」
「うーん・・・わかんないです。若くはないと思いますけど」
「もらったとか保護したとか?」
「はい、半年くらい前だったかな、部屋の前の専用庭でニャーニャー鳴いてたんですよ。可哀想だったんで家の中に入れたんです。それからウチに居ついて、ずっと私が飼っています」
「迷い猫かしら?」
「わかんないです。首輪はしてませんでした」
野良猫を保護するなんて、この男、そんなに悪い男でもなさそうだ。

国松の左側3メートル位のところに警察官が折りたたみ椅子に座っていた。手にはメモ用紙とボールペン。だが、何もメモしていないようだった。真左子と国松の会話を聞いて何を感じたのか?それはわからない。警察官は無表情のままだった。
「私の方で預かったらすぐ動物病院に連れてって検査しますけど、いいですか?」
「もちろんです。費用はお支払いしますんで・・・」
国松は真左子の眼をじっと見つめた。国松はチャー子のことを心の底から心配しているようだった。可愛がっているのだろう。虐待するような男には見えない。いちおう信用してもよいかもしれない。
真左子は言った。
「ところで私はどうやってチャー子ちゃんを部屋から出せばいいんですか?」
「実は部屋の鍵を警察に没収されちゃってるんですよ。だから鍵はお渡しできないんです。警察が私の部屋に捜索に入るときにチャー子を保護してもらえますか?」
不安そうな顔の国松。そのグレーのスェットシャツから汗臭い臭いが漂ってきそうだった。
「いつ警察が国松さんの部屋に入るんですか?」
「まだわかんないです。谷崎弁護士が猫が餓死してしまうんで部屋の捜索を早くやってくださいって警察と交渉してるんです。いつ警察が部屋に入ってくれるか谷崎弁護士に聞いてもらえますか?」
少し考えた末、真左子は答えた。「わかりました」
この男は留置場の中にいる限り、何もできないのだ。外部との連絡も。
国松はスェットパンツの両膝に握り拳をのせ、身を乗り出して真左子の顔をすがるように見つめた。
一瞬、沈黙が部屋の中を覆う。
大体の事情は飲みこめた。
「それでは私、帰りますので」真左子は国松に言って席を立った。
ドアの前で振り向くと国松は言った。
「本当に申し訳ありません。チャー子を助けてください。よろしくお願いします。費用は必ずお支払します」
国松はアクリルボードの向こうで起立して腰から頭を下げた。
真左子が廊下に出ると、ほぼ同時に警察官も廊下に出て来た。
「面会終わりました。ありがとうございます」
と、真左子は言ったが、警察官は何も答えなかった。
廊下の隅の長椅子にスーツ姿の男が座っていた。膝に書類の青いファイルを載せている。襟のバッジからすると弁護士だろう。イライラした様子で面会の順番を待っていた。
真左子は肌寒い冷気と湿気のこもった麻布西警察署を出て六本木駅に戻り、大江戸線に乗って家に向かった。
N駅に着いたころには雨がポツポツ降り始めていた。
低く垂れこめた厚い灰色の雲の隙間から鈍い陽光が透けて見えた。
部屋に戻ってすぐ真左子は谷崎弁護士に電話した。10回呼出音が鳴ったが、「お繋ぎすることができませんでした」とのメッセージ。
悪態をついて電話を切る。
真左子は苛立った。
警察が部屋の鍵を渡してくれないというのも困ったものだ。いつまで待てばよいのだろう。ゴハンをあげなくなってからもう今日で2日目。あと3、4日が限界ではないか。早くチャー子をレスキューしなければ・・・。

ガラケーを握ったまま次に嘉村に電話。
もしチャー子を無事保護できた場合に、預かってもらえるか聞くためだ。
嘉村の家には既に9匹の保護猫がいる。大丈夫だろうか?
3回の呼出音で電話に出た嘉村に、飼い主が警察に捕まって部屋に残された猫をレスキューすることを伝えた。
「レスキューできたら預かってもらっていいですか?」
真左子は尋ねた。
「何匹?」
「一匹です」
「一匹ならいいわよ。隔離部屋があるから。しばらくそこに居てもらうことになるけど」
「ありがとうございます!」
真左子は礼を言った。
「動物病院の検査代とかゴハン代とか、費用をちゃんと払ってもらわなきゃ駄目よ。一筆もらったの?」
嘉村は言った。
「一筆?」
「そうよ。もらってないの?」
「・・・・・・ちゃんと払うって言ってましたから・・・」
「そんなのあてになんないわよー。また騙されるわよ、あなた」
嘉村は呆れた様子で言った。
夜の10時過ぎになって真左子のガラケーが振動した。「谷崎弁護士」の表示である。
ドキッとした。1回深呼吸してからガラケーを取る。
谷崎弁護士は早口で言った。
「すいません。お電話いただいちゃって。猫が餓死してしまうんで早く部屋の捜索をしてくれって警察に頼んでいたんですけど、警察も事情を分かってくれて、明日の朝10時にそちらのマンションに行くそうです。吉崎さんのことは話しておきましたので、マンションの前で待っててください。警察から猫の引渡しを受けられると思います」
「わかりました。マンションの前で待っていればいいんですね」
「はい、お願いします」
よしっ、明日の朝を待つだけだ。
翌朝9時40分、真左子はキャリーケースを持って1階に降り、マンションの正面玄関の前で警察が来るのを待った。雨は上がっていたが夜中に降った強い雨のせいで路面は濡れていた。
10分ほどして、正面玄関の前に2台の地味な車が滑り込んできた。
パトカーではなく普通の乗用車だった。
4人のスーツ姿の男と、黒いジャンパー姿で肩からカメラを提げて手に工具箱を持った男が車から降りてきた。
普通のサラリーマン風には見えない。眼つきが鋭すぎる。刑事だろう。
短髪でいかつい40代位の男がキャリーケースを手に持った真左子に近づいてきた。
「吉崎さんですか? 戸塚警察署の友田です」
男は黒い手帳を開いて見せた。銀色のバッジのようなものが貼りついていた。よく見ようとしたが、2秒ほどで男はパタンと手帳を閉じてしまい、所属や氏名を確認することはできなかった。
「猫を保護される方ですよね」
ぶっきらぼうに刑事は言った。
「はい」
「私ら、これから国松の部屋の捜索に入りますんで、猫がいたら捕まえて持ってきます。ここで待っててくれますか?」
「はい」
真左子はキャリーケースを刑事に手渡した。
チャー子を捕まえることができるだろうか?真左子は半信半疑だった。隠れられたら捕まえるのは大変だ。
刑事たちはゾロゾロと国松の105号室のドアの方に向かって行った。
20分ほどエントランスで待っているとさっきの刑事が猫が入ったキャリーケースを持って小走りに出てきた。
「捕まえたんで・・・」
刑事はキャリーケースを真左子に差し出した。
「ありがとうございます。暴れたりしませんでしたか?」
「いや、大丈夫でした。大人しかったですよ」

真左子はキャリーケースのフタを開けた。黒白タキシードの猫が不安そうな表情で真左子を見上げた。
見た感じ、衰弱していない。よかった・・・。無事レスキュー完了。
真左子はキャリーケースのフタから人差し指を入れてチャー子の頭を撫でた。「よかったねー、チャー子。もう大丈夫だよー」
用意してきたちゅ~るを指先に付けて、チャー子の鼻先に持っていったが、プイッと横を向いて舐めようとはしなかった、まだ緊張しているのだろう。
「あっ」真左子は思わず声を出した。
この猫はどこかで見たことがある。鼻の上の黒い斑点。
近江さんの奥さんの家で見せてもらった写真の子だ。クララに間違いない。
205号室から逃げ出した子。生きてたんだー!
(続く)
著者:弁護士 林太郎
Photo: Hisashi Watabe
第13回 猫救出作戦
「名前は?」
「チャー子です」
「何才ですか?」
「うーん・・・わかんないです。若くはないと思いますけど」
「もらったとか保護したとか?」
「はい、半年くらい前だったかな、部屋の前の専用庭でニャーニャー鳴いてたんですよ。可哀想だったんで家の中に入れたんです。それからウチに居ついて、ずっと私が飼っています」
「迷い猫かしら?」
「わかんないです。首輪はしてませんでした」
野良猫を保護するなんて、この男、そんなに悪い男でもなさそうだ。

国松の左側3メートル位のところに警察官が折りたたみ椅子に座っていた。手にはメモ用紙とボールペン。だが、何もメモしていないようだった。真左子と国松の会話を聞いて何を感じたのか?それはわからない。警察官は無表情のままだった。
「私の方で預かったらすぐ動物病院に連れてって検査しますけど、いいですか?」
「もちろんです。費用はお支払いしますんで・・・」
国松は真左子の眼をじっと見つめた。国松はチャー子のことを心の底から心配しているようだった。可愛がっているのだろう。虐待するような男には見えない。いちおう信用してもよいかもしれない。
真左子は言った。
「ところで私はどうやってチャー子ちゃんを部屋から出せばいいんですか?」
「実は部屋の鍵を警察に没収されちゃってるんですよ。だから鍵はお渡しできないんです。警察が私の部屋に捜索に入るときにチャー子を保護してもらえますか?」
不安そうな顔の国松。そのグレーのスェットシャツから汗臭い臭いが漂ってきそうだった。
「いつ警察が国松さんの部屋に入るんですか?」
「まだわかんないです。谷崎弁護士が猫が餓死してしまうんで部屋の捜索を早くやってくださいって警察と交渉してるんです。いつ警察が部屋に入ってくれるか谷崎弁護士に聞いてもらえますか?」
少し考えた末、真左子は答えた。「わかりました」
この男は留置場の中にいる限り、何もできないのだ。外部との連絡も。
国松はスェットパンツの両膝に握り拳をのせ、身を乗り出して真左子の顔をすがるように見つめた。
一瞬、沈黙が部屋の中を覆う。
大体の事情は飲みこめた。
「それでは私、帰りますので」真左子は国松に言って席を立った。
ドアの前で振り向くと国松は言った。
「本当に申し訳ありません。チャー子を助けてください。よろしくお願いします。費用は必ずお支払します」
国松はアクリルボードの向こうで起立して腰から頭を下げた。
真左子が廊下に出ると、ほぼ同時に警察官も廊下に出て来た。
「面会終わりました。ありがとうございます」
と、真左子は言ったが、警察官は何も答えなかった。
廊下の隅の長椅子にスーツ姿の男が座っていた。膝に書類の青いファイルを載せている。襟のバッジからすると弁護士だろう。イライラした様子で面会の順番を待っていた。
真左子は肌寒い冷気と湿気のこもった麻布西警察署を出て六本木駅に戻り、大江戸線に乗って家に向かった。
N駅に着いたころには雨がポツポツ降り始めていた。
低く垂れこめた厚い灰色の雲の隙間から鈍い陽光が透けて見えた。
部屋に戻ってすぐ真左子は谷崎弁護士に電話した。10回呼出音が鳴ったが、「お繋ぎすることができませんでした」とのメッセージ。
悪態をついて電話を切る。
真左子は苛立った。
警察が部屋の鍵を渡してくれないというのも困ったものだ。いつまで待てばよいのだろう。ゴハンをあげなくなってからもう今日で2日目。あと3、4日が限界ではないか。早くチャー子をレスキューしなければ・・・。

ガラケーを握ったまま次に嘉村に電話。
もしチャー子を無事保護できた場合に、預かってもらえるか聞くためだ。
嘉村の家には既に9匹の保護猫がいる。大丈夫だろうか?
3回の呼出音で電話に出た嘉村に、飼い主が警察に捕まって部屋に残された猫をレスキューすることを伝えた。
「レスキューできたら預かってもらっていいですか?」
真左子は尋ねた。
「何匹?」
「一匹です」
「一匹ならいいわよ。隔離部屋があるから。しばらくそこに居てもらうことになるけど」
「ありがとうございます!」
真左子は礼を言った。
「動物病院の検査代とかゴハン代とか、費用をちゃんと払ってもらわなきゃ駄目よ。一筆もらったの?」
嘉村は言った。
「一筆?」
「そうよ。もらってないの?」
「・・・・・・ちゃんと払うって言ってましたから・・・」
「そんなのあてになんないわよー。また騙されるわよ、あなた」
嘉村は呆れた様子で言った。
夜の10時過ぎになって真左子のガラケーが振動した。「谷崎弁護士」の表示である。
ドキッとした。1回深呼吸してからガラケーを取る。
谷崎弁護士は早口で言った。
「すいません。お電話いただいちゃって。猫が餓死してしまうんで早く部屋の捜索をしてくれって警察に頼んでいたんですけど、警察も事情を分かってくれて、明日の朝10時にそちらのマンションに行くそうです。吉崎さんのことは話しておきましたので、マンションの前で待っててください。警察から猫の引渡しを受けられると思います」
「わかりました。マンションの前で待っていればいいんですね」
「はい、お願いします」
よしっ、明日の朝を待つだけだ。
翌朝9時40分、真左子はキャリーケースを持って1階に降り、マンションの正面玄関の前で警察が来るのを待った。雨は上がっていたが夜中に降った強い雨のせいで路面は濡れていた。
10分ほどして、正面玄関の前に2台の地味な車が滑り込んできた。
パトカーではなく普通の乗用車だった。
4人のスーツ姿の男と、黒いジャンパー姿で肩からカメラを提げて手に工具箱を持った男が車から降りてきた。
普通のサラリーマン風には見えない。眼つきが鋭すぎる。刑事だろう。
短髪でいかつい40代位の男がキャリーケースを手に持った真左子に近づいてきた。
「吉崎さんですか? 戸塚警察署の友田です」
男は黒い手帳を開いて見せた。銀色のバッジのようなものが貼りついていた。よく見ようとしたが、2秒ほどで男はパタンと手帳を閉じてしまい、所属や氏名を確認することはできなかった。
「猫を保護される方ですよね」
ぶっきらぼうに刑事は言った。
「はい」
「私ら、これから国松の部屋の捜索に入りますんで、猫がいたら捕まえて持ってきます。ここで待っててくれますか?」
「はい」
真左子はキャリーケースを刑事に手渡した。
チャー子を捕まえることができるだろうか?真左子は半信半疑だった。隠れられたら捕まえるのは大変だ。
刑事たちはゾロゾロと国松の105号室のドアの方に向かって行った。
20分ほどエントランスで待っているとさっきの刑事が猫が入ったキャリーケースを持って小走りに出てきた。
「捕まえたんで・・・」
刑事はキャリーケースを真左子に差し出した。
「ありがとうございます。暴れたりしませんでしたか?」
「いや、大丈夫でした。大人しかったですよ」

真左子はキャリーケースのフタを開けた。黒白タキシードの猫が不安そうな表情で真左子を見上げた。
見た感じ、衰弱していない。よかった・・・。無事レスキュー完了。
真左子はキャリーケースのフタから人差し指を入れてチャー子の頭を撫でた。「よかったねー、チャー子。もう大丈夫だよー」
用意してきたちゅ~るを指先に付けて、チャー子の鼻先に持っていったが、プイッと横を向いて舐めようとはしなかった、まだ緊張しているのだろう。
「あっ」真左子は思わず声を出した。
この猫はどこかで見たことがある。鼻の上の黒い斑点。
近江さんの奥さんの家で見せてもらった写真の子だ。クララに間違いない。
205号室から逃げ出した子。生きてたんだー!
(続く)
著者:弁護士 林太郎
Photo: Hisashi Watabe