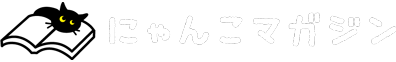第4回 保護猫のロシアンブルー
3月7日の午後10時過ぎ、真左子は日課になった猫のウンコとゲロの見回りを終えて部屋に戻った。この日は午前10時24分に普段はほとんどマンション敷地内には入ってこないグレー白のチビが正面扉の外にいるのを見つけた。午後6時45分には自転車置場で15粒くらいのカリカリが地面に置かれているのを見つけた。
真佐子はパソコンで多津子にメールした。
「自転車置場で猫に餌やりをしている人がいるみたいです。今日もカリカリが15粒くらい置かれているのを見つけました。7階の米津さんの奥さんか息子じゃないですよね?」

第4回 保護猫のロシアンブルー
3月7日の午後10時過ぎ、真左子は日課になった猫のウンコとゲロの見回りを終えて部屋に戻った。この日は午前10時24分に普段はほとんどマンション敷地内には入ってこないグレー白のチビが正面扉の外にいるのを見つけた。午後6時45分には自転車置場で15粒くらいのカリカリが地面に置かれているのを見つけた。
真佐子はパソコンで多津子にメールした。
「自転車置場で猫に餌やりをしている人がいるみたいです。今日もカリカリが15粒くらい置かれているのを見つけました。7階の米津さんの奥さんか息子じゃないですよね?」

午後11時半ころ寝る前にパソコンを開けてみると多津子から返事が来ていた。
「こんど米津さんの奥さんにあったらそれとなく聞いてみるね(^_-)」と書いてあった。
多津子は続けて書いていた。
「それと、このマンションができてからずっと住んでいて、長年管理組合の理事をしていた309号室の近江さんに話しを聞けたら、今回のことでいろいろ参考になることがあるかもしれないと思います。理事長の大竹のこともよく知っていると思います。なぜ管理組合がこんな裁判を起こしたのか分かるかも」
真左子は多津子からのメールを「餌やり禁止裁判」というフォルダに移し、パソコンを閉じた。
309号室の近江さん。奥さんのことは顔だけは知っている。70代の女性。エントランスで会えば挨拶するくらいだが、きちんと挨拶する人だ。話したことはないが嫌な感じのする人ではない。ご主人さんの顔は思い当たらない。会ってみる価値はあるかもしれない。真左子は思った。もちろん先方が会ってくれればの話だけれど。
翌日の午前11時過ぎ、真左子は多津子のメールに書いてあった近江さんの部屋の固定電話の番号にガラケーで電話を入れた。
5回ほどの呼出音で近江さんの奥さんは出た。「近江でございます」きちんとした口調だった。
真左子は自分の部屋番号と名前を名乗り、「マンションの管理組合のことでちょっとお話しをお伺いしたいことがありまして...」そう切り出してみた。
「管理組合? うちはもう何にもやってないわよ、管理組合関係は。何かあったの?」
「実は、管理組合から裁判を起こされてまして...」
「あー、大竹さん、またやってんのね。やーねー」
近江さんの奥さんは少し間を置いてから言った。
「いいわ、昼過ぎの1時ころ来てくれる? 3時ころから病院に行かなくちゃならないのよ、主人が入院してるから」
サバサバした感じだった。東京生まれの東京育ちの人に特有のイントネーションだ。
「それでは1時ころ伺いますので。ありがとうございます」
そう言って真左子は電話を切った。
午後1時過ぎ、真左子は部屋を出て309号室の近江さんの部屋のインターホンを押した。奥さんが出てきてリビングに通された。12畳くらいの広さだろうか。それとなく見回してみる。家具はどれも決して新しい物ではなかったが、綺麗に手入れされていた。おそらくこの奥さんは綺麗好きなのだろう。
真佐子は奥さんに指指されるままソファーに座った。
奥さんはキッチンでコーヒーか紅茶を入れはじめたようだった。
「どうかお構いなく」真左子は言った。
ソファーの前にはちょうど膝の高さのテーブルがあった。右側には32インチくらいのテレビのディスプレイが置かれていて、昼の民放のテレビ番組が映し出されていた。
和歌山県で19歳の看護学校生が自宅のアパートで絞殺されたらしかった。画面には看護学校生が住んでいたアパート。何の変哲もないごく普通のアパートだった。上に4戸、下に4戸。
同じアパートの住民の首から下が映し出された。未明に人が争う物音と「助けてー」「ギャー」という女性の悲鳴を聞いたと話していた。風呂場の窓から外を見てみると、上下黒っぽいジャージー姿で身長170センチ位の若い男が走り去るのを見たという。
リポーターによれば、警察は看護学校生の交友関係を中心に捜査を進めているということだった。
真左子はディスプレイから目を離し、部屋の左斜め前にあるサイドボードに目を移した。下にグレーの猫がちょこんと座っているのを見つけた。
「猫がいるんだ」真左子は思った。
この部屋は彼(彼女)のテリトリーである。
不躾な態度を取れば後でとんでもない仕返しがある。真左子はそのことを経験上よく知っていた。
真左子は小さい声で「ニャオ」とあくまでも下手にフレンドリーに挨拶してみた。
猫もこちらを見た。
真左子はもう一度小さい声で「ニャオ」と声を掛けてみた。
すると猫はツッ、ツッ、ツッとこちらに向かって歩いてきた。
そして真左子の膝の下あたりに頭を軽くゴツンとぶつけ、頭の辺りを擦りつけてきた。
人懐っこい子だ。この子なら私がこの部屋へ来るのも許してくれるかもしれない。
真左子が頭を撫でると猫は嬉しくて仕方ないらしく、絨毯にゴロンと横になり左の横腹をこちらに向けた。「いい子ちゃんねー」そう言いながら真左子は猫の頭と腹を交互に撫でた。
12歳くらいだろうか。ロシアンブルーに見える。ハンサムな顔立ちをしていた。
真左子は「猫さんがいるんですね。いくつですか?」と奥さんに尋ねた。
「推定で16歳くらいだと思うわ」奥さんはキッチンで後ろ向きのまま答えた。
『推定』という言葉で真左子はピンときた。この猫はペットショップで買ってきた猫ではない。正確な生年月日が分からないのだ。
真左子は少しホッとした。ソファーに背を沈めて右手でゆっくり布の感触を確かめた。
「もう一匹いるんだけどね」奥さんは言った。「その子は人が来ると絶対出てこないのよ。向こうの部屋に隠れてると思うわ」
前方に別の部屋が見える。部屋の境に布のすだれが掛かっていて下半分しか見えない。家具にベージュの敷物が掛けてあった。
もう一匹の猫はこの部屋に隠れているのかもしれない。
(続く)