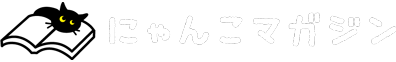第12回 閉じ込められた猫
真左子は地下鉄大江戸線の六本木駅で降り、3番出口から地上に出た。
首都高の高架下に沿って鋪道を左へ歩いていく。首都高に遮られ空は半分しか見えない。空の色は高架下のコンクリートの色と同じ灰色だった。境い目が分からない。
居酒屋や銀行のキャッシュコーナーを過ぎて、50メートルほど歩いたところに麻布西警察署はあった。
古い建物。この建物も灰色だった。周りの風景の色に見事に溶け込んでいる。「やさしさが走るこの街この道路」の垂れ幕の文字と、その下に描かれた陽気なキャラクターが浮いていた。
正面玄関の前にはコートを着た警官が長い棒を両手で持って不機嫌そうに立っていた。

ことの発端は、昨日の夜10時過ぎに真左子のガラケーに突然かかってきた1本の電話だった。男の声。
「えー私、弁護士の谷崎と申しまして、国松幸太郎さんという方の弁護人をしております」
最初は何のことだかさっぱり分からなかった。
弁護士の谷崎という男は続けた。
「国松さんは吉崎さんと同じマンションの1階に住んでいるんですけども、昨日、会社の仕事の関係で逮捕されたんですよ。それで今、麻布西警察署の留置場にいるんです」
「・・・・・・」
「それで何で吉崎さんに電話させていただいたかというと、国松さん、猫を飼っていて部屋に猫がいるんですよ」
「猫?」
「はい」
「何号室の方ですか?」
「105号室です」
105号室の国松さん。真左子には心当たりがなかった。
「猫は何匹いるんですか?」
「1匹です。国松さんは独り暮らしなんですけど、昨日の朝に猫に餌をあげて、午後2時過ぎに警察に逮捕されたんで、今は誰も猫に餌をあげる人がいないんです。それで国松さんは猫のことが心配で、吉崎さんに猫を預かってもらえないかと・・・」
「どうして私に電話してるんですか?」
「国松さんはマンションの各部屋に配布された管理組合の理事会議事録を見て、吉崎さんが猫のことで管理組合と裁判をやっていることを知ってるんですよ。それでマンション周辺の野良猫の世話をしている吉崎さんに国松さんの猫の預かってもらえないかと・・・」
「私の電話番号を誰から聞きました?」
「管理組合の大竹さんに教えていただきました」
「大竹さん?!」
大竹という名前を聞いて、真左子は背筋に寒気が走った。
確かにマンションの管理組合には自分の携帯電話の番号を届けてある。詐欺師の大竹に携帯電話の番号という、もろに個人情報を知られていることが不快だったが、すぐに気を取り直した。いざとなったら携帯電話を捨てればよい。
弁護士の谷崎の話によれば、国松幸太郎が逮捕されたのが昨日の昼すぎ。もう丸1日以上、猫にゴハンをあげていないことになる。1週間くらいなら飢え死にすることはないとは思うが、心配だ。1匹なら何とかなる。一刻も早く猫を保護してあげなければ。真左子は思った。
真左子は尋ねた。
「国松さんという方はいつまで警察署にいるんですか?」
「誤認逮捕であることが明らかなんで、長くても20日間位だと思います。その後は釈放されます」
弁護士の谷崎はごく事務的な口調で言った。
「20日間だと餓死してしまいますよ。とにかく早く猫をお預かりしたいと思います」
「お願いできますか? それで、その件で国松さんは吉崎さんに警察署まで面会に来ていただきたいと言ってるんですが、会っていただけますか?」
「普通の人でも面会できるんですか?」
「できます」
弁護士の谷崎は答えた。そして真左子に面会の予約の取り方を教えた。
一晩明けた今日の朝9時、真左子は弁護士の谷崎から教えられたとおり、麻布西警察署に電話して「留置係」に繋いでもらった。
「吉崎真左子と申しますが、そちらに捕まっている国松幸太郎さんに面会したいんですけど」
国松とどういう関係なのか聞かれたので、同じマンションの住人であり、国松が部屋に残された猫の世話のことで面会を希望していることを伝えた。
しばらく間をおいてから電話口の相手は言った。
「それでは今日の午後2時に来てください」
正面玄関のガラス扉を開けて真左子は麻布西警察署の建物内に入っていった。受付カウンターのブルーの制服を着た女性警察官に、捕まっている国松幸太郎さんに面会に来たと告げた。
「予約はしてありますか?」
疑り深そうな目で真左子を見ながら女性警察官は言った。
「はい」
女性警察官は右手で机の上の受話器を取り、内線で留置係に電話して何かを話していた。
電話を切って、女性警察官はフロアの隅のエレベーターを指さして言った。
「6階に行ってください」
真左子は薄汚れたエレベーターに乗って6階に上がる。
箱の中には背中に「警視庁」と書いてある黒いベストを着た男性警察官が2人乗っていた。
一人はいかにも柔道をやっていそうなガッチリとした大きな体で、もう一人は小柄だった。
真左子は6階で降りて廊下に出た。
汗とトイレの臭いが混じったような湿った空気がこもっていて思わず足を止める。
廊下を歩き、ドアの開いた部屋の中にいた警察官に恐る恐る「国松さんに面会に来たんですけど・・・」と言うと、受付からの内線の電話で分かっていたらしく、「あー国松ね、こっちへ」と言われ、三畳間ほどの広さの小部屋に通された。
その小部屋の机で面会申請書に住所・氏名などを書かされ、印鑑を押した。
警察官は面会申請書を手に持って小部屋から出て行き、しばらくすると戻ってきて「こっちへ」と素っ気なく言って真左子を廊下の突き当たりにある面会室に案内した。
面会室の中は、厚さ1センチくらいの透明なアクリルボードで真ん中を仕切られていた。アクリルボードの手前の長細い筆記台の椅子に真左子が座ると、ちょうど口の高さのところのアクリルボードに小さい円形の穴がいくつも開いていた。
5分ほど座って待っていると、グレーのトレーナーの上下を着て無精ヒゲ姿の男が警察官に連れられて仕切りの向こうのスペースに入ってきた。そして、アクリルボードを隔てた真左子の正面に座った。
色白で小柄な40代くらいの男。ネクタイをすれば、普通の勤め人にしか見えないだろう。
男は照れくさそうに苦笑いを浮かべて言った。
「105号室の国松といいます。すいません、来ていただいて」
国松はペコンと頭を下げた。
「実は私の部屋に猫がいるんです」
「谷崎弁護士から聞きました。猫にゴハンをあげてないんですよね」
「はい。こんなことになっちゃったんで・・・」
「いつからあげてないんですか?」
「24日の朝の出勤前の7時にフードと水の皿を置いたきりですから、もう丸2日以上あげてないです」
国松はすがるような眼つきで真左子の眼を凝視した。
「どんな猫なんですか?」
「黒白の猫です」
(続く)
著者:弁護士 林太郎
第12回 閉じ込められた猫
真左子は地下鉄大江戸線の六本木駅で降り、3番出口から地上に出た。
首都高の高架下に沿って鋪道を左へ歩いていく。首都高に遮られ空は半分しか見えない。空の色は高架下のコンクリートの色と同じ灰色だった。境い目が分からない。
居酒屋や銀行のキャッシュコーナーを過ぎて、50メートルほど歩いたところに麻布西警察署はあった。
古い建物。この建物も灰色だった。周りの風景の色に見事に溶け込んでいる。「やさしさが走るこの街この道路」の垂れ幕の文字と、その下に描かれた陽気なキャラクターが浮いていた。
正面玄関の前にはコートを着た警官が長い棒を両手で持って不機嫌そうに立っていた。

ことの発端は、昨日の夜10時過ぎに真左子のガラケーに突然かかってきた1本の電話だった。男の声。
「えー私、弁護士の谷崎と申しまして、国松幸太郎さんという方の弁護人をしております」
最初は何のことだかさっぱり分からなかった。
弁護士の谷崎という男は続けた。
「国松さんは吉崎さんと同じマンションの1階に住んでいるんですけども、昨日、会社の仕事の関係で逮捕されたんですよ。それで今、麻布西警察署の留置場にいるんです」
「・・・・・・」
「それで何で吉崎さんに電話させていただいたかというと、国松さん、猫を飼っていて部屋に猫がいるんですよ」
「猫?」
「はい」
「何号室の方ですか?」
「105号室です」
105号室の国松さん。真左子には心当たりがなかった。
「猫は何匹いるんですか?」
「1匹です。国松さんは独り暮らしなんですけど、昨日の朝に猫に餌をあげて、午後2時過ぎに警察に逮捕されたんで、今は誰も猫に餌をあげる人がいないんです。それで国松さんは猫のことが心配で、吉崎さんに猫を預かってもらえないかと・・・」
「どうして私に電話してるんですか?」
「国松さんはマンションの各部屋に配布された管理組合の理事会議事録を見て、吉崎さんが猫のことで管理組合と裁判をやっていることを知ってるんですよ。それでマンション周辺の野良猫の世話をしている吉崎さんに国松さんの猫の預かってもらえないかと・・・」
「私の電話番号を誰から聞きました?」
「管理組合の大竹さんに教えていただきました」
「大竹さん?!」
大竹という名前を聞いて、真左子は背筋に寒気が走った。
確かにマンションの管理組合には自分の携帯電話の番号を届けてある。詐欺師の大竹に携帯電話の番号という、もろに個人情報を知られていることが不快だったが、すぐに気を取り直した。いざとなったら携帯電話を捨てればよい。
弁護士の谷崎の話によれば、国松幸太郎が逮捕されたのが昨日の昼すぎ。もう丸1日以上、猫にゴハンをあげていないことになる。1週間くらいなら飢え死にすることはないとは思うが、心配だ。1匹なら何とかなる。一刻も早く猫を保護してあげなければ。真左子は思った。
真左子は尋ねた。
「国松さんという方はいつまで警察署にいるんですか?」
「誤認逮捕であることが明らかなんで、長くても20日間位だと思います。その後は釈放されます」
弁護士の谷崎はごく事務的な口調で言った。
「20日間だと餓死してしまいますよ。とにかく早く猫をお預かりしたいと思います」
「お願いできますか? それで、その件で国松さんは吉崎さんに警察署まで面会に来ていただきたいと言ってるんですが、会っていただけますか?」
「普通の人でも面会できるんですか?」
「できます」
弁護士の谷崎は答えた。そして真左子に面会の予約の取り方を教えた。
一晩明けた今日の朝9時、真左子は弁護士の谷崎から教えられたとおり、麻布西警察署に電話して「留置係」に繋いでもらった。
「吉崎真左子と申しますが、そちらに捕まっている国松幸太郎さんに面会したいんですけど」
国松とどういう関係なのか聞かれたので、同じマンションの住人であり、国松が部屋に残された猫の世話のことで面会を希望していることを伝えた。
しばらく間をおいてから電話口の相手は言った。
「それでは今日の午後2時に来てください」
正面玄関のガラス扉を開けて真左子は麻布西警察署の建物内に入っていった。受付カウンターのブルーの制服を着た女性警察官に、捕まっている国松幸太郎さんに面会に来たと告げた。
「予約はしてありますか?」
疑り深そうな目で真左子を見ながら女性警察官は言った。
「はい」
女性警察官は右手で机の上の受話器を取り、内線で留置係に電話して何かを話していた。
電話を切って、女性警察官はフロアの隅のエレベーターを指さして言った。
「6階に行ってください」
真左子は薄汚れたエレベーターに乗って6階に上がる。
箱の中には背中に「警視庁」と書いてある黒いベストを着た男性警察官が2人乗っていた。
一人はいかにも柔道をやっていそうなガッチリとした大きな体で、もう一人は小柄だった。
真左子は6階で降りて廊下に出た。
汗とトイレの臭いが混じったような湿った空気がこもっていて思わず足を止める。
廊下を歩き、ドアの開いた部屋の中にいた警察官に恐る恐る「国松さんに面会に来たんですけど・・・」と言うと、受付からの内線の電話で分かっていたらしく、「あー国松ね、こっちへ」と言われ、三畳間ほどの広さの小部屋に通された。
その小部屋の机で面会申請書に住所・氏名などを書かされ、印鑑を押した。
警察官は面会申請書を手に持って小部屋から出て行き、しばらくすると戻ってきて「こっちへ」と素っ気なく言って真左子を廊下の突き当たりにある面会室に案内した。
面会室の中は、厚さ1センチくらいの透明なアクリルボードで真ん中を仕切られていた。アクリルボードの手前の長細い筆記台の椅子に真左子が座ると、ちょうど口の高さのところのアクリルボードに小さい円形の穴がいくつも開いていた。
5分ほど座って待っていると、グレーのトレーナーの上下を着て無精ヒゲ姿の男が警察官に連れられて仕切りの向こうのスペースに入ってきた。そして、アクリルボードを隔てた真左子の正面に座った。
色白で小柄な40代くらいの男。ネクタイをすれば、普通の勤め人にしか見えないだろう。
男は照れくさそうに苦笑いを浮かべて言った。
「105号室の国松といいます。すいません、来ていただいて」
国松はペコンと頭を下げた。
「実は私の部屋に猫がいるんです」
「谷崎弁護士から聞きました。猫にゴハンをあげてないんですよね」
「はい。こんなことになっちゃったんで・・・」
「いつからあげてないんですか?」
「24日の朝の出勤前の7時にフードと水の皿を置いたきりですから、もう丸2日以上あげてないです」
国松はすがるような眼つきで真左子の眼を凝視した。
「どんな猫なんですか?」
「黒白の猫です」
(続く)
著者:弁護士 林太郎